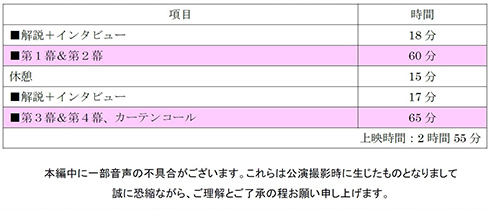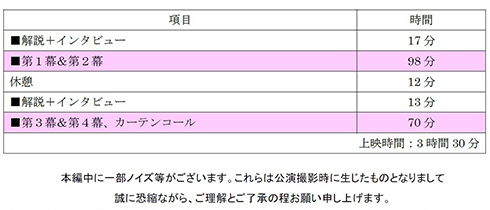コラム
伝統と革新、ロイヤル・バレエ&オペラの新シーズン
コヴェント・ガーデンの進化が止まらない。長年「ロイヤル・オペラ・ハウス」の名でイギリスの、いや世界のオペラとバレエ上演を牽引してきた劇場が、このたび「ロイヤル・バレエ&オペラ」と名称を変え、2024〜25年のシネマシーズンを始める。遠方のファンでも、まるで劇場内(それも特等席)にいるかのような感覚を味わえるだけでなく、関係者インタビューや稽古場での様子の紹介、SNSでのハッシュタグ付き投稿によるファン同士の交流は、映画館放映ならではの体験といえよう。劇場に来る人のみならず、全世界のファン、そしてこれからファンになる潜在的観客層をも視野に入れたシネマシーズンは、新生ロイヤル・バレエ&オペラにおいても大きな魅力の一つである。
さて、2024〜25年のシーズンには、ロイヤル・オペラの音楽監督の交代という、もう一つの新しさもある。2002年からの長期にわたってロイヤル・オペラの音楽監督を務めたアントニオ・パッパーノが昨シーズンで勇退し、代わって新音楽監督に就任したのがヤクブ・フルシャ。43歳となる彼は2018年にロイヤル・オペラでビゼーの《カルメン》を振っており、すでに数々のオペラ・ハウスでの経験を有する。新体制下のシネマシーズンの1作目は、モーツァルトの《フィガロの結婚》である。ロイヤル・オペラでは2006年からデイヴィッド・マクヴィカー演出によるプロダクションを上演しており、大好評を得てきた。今回の上演を指揮するのは、ベテラン指揮者のジュリア・ジョーンズである。
《フィガロ》の時代を越える人間模様と社会風刺
《フィガロの結婚》の最大の魅力は、生き生きとした人間模様によって描き出される、喜劇に見せかけた社会批判だろう。立場を利用して情事を楽しもうとする貴族を、頭の切れる床屋の家来がギャフンと言わせる、というこのオペラの物語は、現代の観客からするとコミカルに見える。しかし、この作品が上演された18世紀末は、ヨーロッパの封建的な貴族社会が危機を迎えつつあった時期だった。絶対視されていた貴族たちの立場は、揺らがないものでは決してない。実際、原作となったボーマルシェの戯曲にはたびたび上演禁止令が出ている。
この点を踏まえると、マクヴィカーがオープニングの稽古場インタビューで「歌手たちに、これは喜劇ではないと言っています」と語る理由が明確になる。作中の人物たちは、皆それぞれの欲求と感情を持ち、自分の正しさのために行動する。そのさまが真剣であればあるほど、観客として物語世界を外から眺める私たちにとっては、物語の状況が滑稽に見える。そしてその視点によって、観客を取り巻く現実社会の滑稽さに気づくのである。
だからこそ、200年前の作品だとしても、現代的な読み替えはマクヴィカーには不要だったのだろう。むしろ、歌手たちの自然な演技によって個々の人物の人間的側面が明確になり、どんな時代にも共通する人間の弱さや愚かさ、そして生きる力が、モーツァルトの音楽とともに示されていく。
歌手陣の活躍が光るプロダクション
今回のフィガロ役を務めるのは、イタリア出身で演劇俳優としての経験を持つバリトンのルカ・ミケレッティである。「音楽に命を吹きこむために、言葉を正しく扱う必要がある」と語るように、第1幕のカヴァティーナ「もしも踊りをなさりたければ」では、スザンナを心配しつつ伯爵の企みに憤慨するフィガロの心情を表情豊かに聴かせる。スザンナ役は当初イン・ファンの予定だったが、収録日は体調不良により降板し、若手コロラトゥーラのシボーン・スタッグが歌っている。終盤のフィガロとの騙し合いののち、伯爵夫人のふりをしてアルマヴィーヴァ伯爵をハメる際の声の切り替えも楽しい。その伯爵を演じるヒュー・モンタギュー・レンドールは、今後の活躍が大いに期待される躍進中のバリトン。他にも、伯爵夫人のマリア・ベントソンの気品溢れる歌唱、恋に恋するケルビーノ役のジンジャー・コスタ・ジャクソンが歌う「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」など、充実期にある歌手陣を中心とする公演は聴きどころも満載だ。
「モーツァルトを上手に演じるのは簡単なことではありません」とマクヴィカーは語る。しかし、その難しさに全力で挑んでいるプロダクションだからこそ、ロイヤルの《フィガロ》は、鑑賞後の観客に高い充実感をもたらしてくれるだろう。